今回は脳振盪のメカニズム評価、そして評価ツールであるVOMSについて書いていきたいと思います。
みなさん、
脳振盪の時にはどのような評価をされていますか?
よく聞く評価ツールとしては、
SCATやImPACT test、cogsportsでしょうか?
そもそも
アメフトやラグビーなどのコンタクトスポーツ以外ではあまり使う機会は少ないかもしれませんね。
しかし、サッカーやバスケ、野球でも脳振盪が起こる可能性は十分ありますし、
それに対して万全の準備をすることはもちろん必要ですよね。
そして、今回紹介するのは
VOMS(Vestibular/Ocular Motor Screening)と呼ばれる脳振盪評価テストです。
僕がこの評価テストを知ったのは、
アメリカで大学院に通っているときに学会で初めて知りました。
実技を中心とした
日本で学生トレーナーとして活動しているときは、
SCATとcogsportsしか知らなかったので、
当時はこんなツールもあるのかーって感じでした。
実際自分が使ってみて、
エビデンスベースの評価テストでもあるので、
非常に有効なものであると個人的に考えています。
では、VOMSについて一緒に見ていきましょう。
VOMSとは?
VOMSとは(Vestibular/Ocular Motor Screening)のことを指し、
日本語で言うと、前庭/眼球動作スクリーニングとなります。
脳振盪後は前庭と眼球運動の異常が多く見られ、それを評価し、脳振盪の判断することを目的としたテストになっています。
必要なものは、
メトロノーム・メジャー・14pointのターゲット
このテストはバランス・視覚・動作を評価するもので、5つの項目から構成されています。
- Smooth pursuits パスート
- Saccades(horizontal and vertical) サッケード(水平・垂直)
- Convergence 輻輳(cm)
- Vestibular ocular reflex(horizontal and vertical) 前庭動眼反射(水平・垂直)
- Visual motion sensitivity/Vestibular ocular reflex cancellation 前庭動眼反射抑制
これら5つの項目をそれぞれ行うことによって脳振盪を評価します。
下の表は評価の時に使用するスケール(0-10)になります。

そもそも脳振盪は、日本ではあまり重要視されない傾向がありますが、
適切な対応をしないと命にも関わる重大な傷害です。
そして、その脳振盪を正しく評価することが何よりも大切になってきます。
いくつか評価をする方法がありますが、その評価方法の1つがVOMSとなります。
では、次に脳振盪そのものについて見ていきましょう。
脳震盪のメカニズム
では脳振盪とはどのようなものなのでしょうか?
脳振盪とは、
外部からの衝撃によって脳が頭蓋骨内で急激に揺れることで起こる外傷性の脳傷害(TBI)です。
急激な脳の揺れは、脳の脳細胞のダメージや脳内で生理学的な変化が起きてしまいます。2)
日本は特にですが、
まだまだ脳振盪の対して甘い考えの人が多い印象がありますが、脳振盪は深刻な脳傷害であることを認識しなくてはいけません。
動画内でもあるように脳振盪はCoup injuryとCotre-coup injuryの2つがあり、
衝撃を受けた場所で起こるCoup injuryと衝撃を受けた反動で反対側の部位が損傷を受けるCotre-coup injuryがあります。
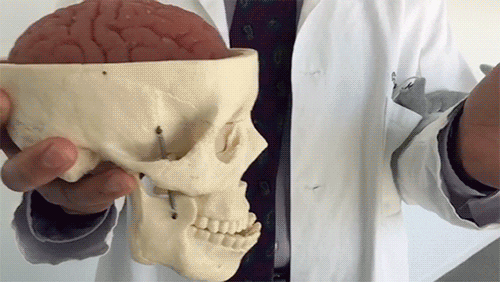

さて、
ここで一つ面白い動画を見つけました。
どこの細胞がダメージを受けるのでしょうか?
衝撃を受けった場所?Coup? Contra-coup?
実は一番ダメージを受けるのは脳梁という説があります。
エビデンスではないのですが、面白い動画を見つけました。(日本語訳あり)
https://www.ted.com/talks/david_camarillo_why_helmets_don_t_prevent_concussions_and_what_might/transcript?language=ja
このTEDのプレゼン(特に8:00〜)では、
脳振盪のダメージが脳のどの部位に起こるのかを解析しています。
もちろん、衝撃自体も大きな問題にはなると思うのですが、
ここでは脳がストレッチされることによって大きなダメージを受けると言われています。
そして、ダメージを最も受けやすいのが、脳梁と言われています。

動画内でも解説されていますが、慢性外傷性脳症がある元アメリカンフットボール選手は、
脳梁の密度が極端に少ないとも言われています。
この現象が慢性的な脳障害の原因ではないかと言われています。
ただ、様々な考察がされていますが、
実際のところは詳しくはわかっていないのが現状です。
脳振盪のサイン
脳振盪後には特定のサインが現れます。
もちろん、サインがないからといって脳振盪ではないとは断定はできませんが、
これらのサインがあれば、脳振盪の疑いがあると言って良いでしょう。
- 受傷後と受傷前のことが思い出せない
- ぼんやりする・ぼーっとする
- 指示を忘れる・混乱する・ポジションや試合内容、対戦相手がわからない
- ぎこちない動き
- 返答が遅い
- 気絶
- 性格・態度の変化(泣く・怒るなど)
では、ここで僕の実体験を書きます。
僕が大学でアメリカンフットボール部で実習をしていた時のことです。 試合形式の練習でディフェンスの選手がオフェンスの選手にタックルをしました。 その後、デフェンス選手の起き上がりが遅かったのですが、 その選手は自分でサイドラインに戻ってきました。 しかし、その選手に問診にいくと、その選手は通常では考えられないような混乱した様子でした。 僕はとりあえず、後ろのベンチに座らせ、少し話しをしようとしました。しかし、 その後、その選手はなんと泣き出したのです。 もちろん、通常ではありえない事態に僕も慌てましたが、 ボスの指示のもと練習にはOUTさせ、そのまま病院へと搬送されました。
このようなことも起きることが考えられるのです。
実際どのような症状が現れるかはわかりません。
しかし、どのような場合でも冷静に評価し、判断することが必要なのです。
近年ではビデオ判定などにより、医師が判断することができるようになりましたね。
もちろん、どのテストも完璧なものはありませんが、限りなく完璧を目指す必要はありそうですね。
脳振盪の主訴
次の脳振盪後の主訴について説明していきたいと思います。
脳振盪後の選手が訴える主訴として考えられるものとして、
- 頭痛または圧迫されている感覚
- 吐き気
- ふらつき、ものが二重に見える
- 光や音に敏感
- モヤがかかったような感覚
- 集中できない、記憶障害
- 気分が悪い、いつもと違う感じ
また、脳振盪後には急変の可能性もあるので、
その日は一人で過ごさないようにする必要もあります。
親が同居している場合では問題ありませんが、
一人暮らしの場合などは誰かに付き添ってもらうことが大切です。
また、運転などもするべきではありません。
SCATの最後にも脳振盪後のアドバイス欄があるので、参考にすると良いと思います。
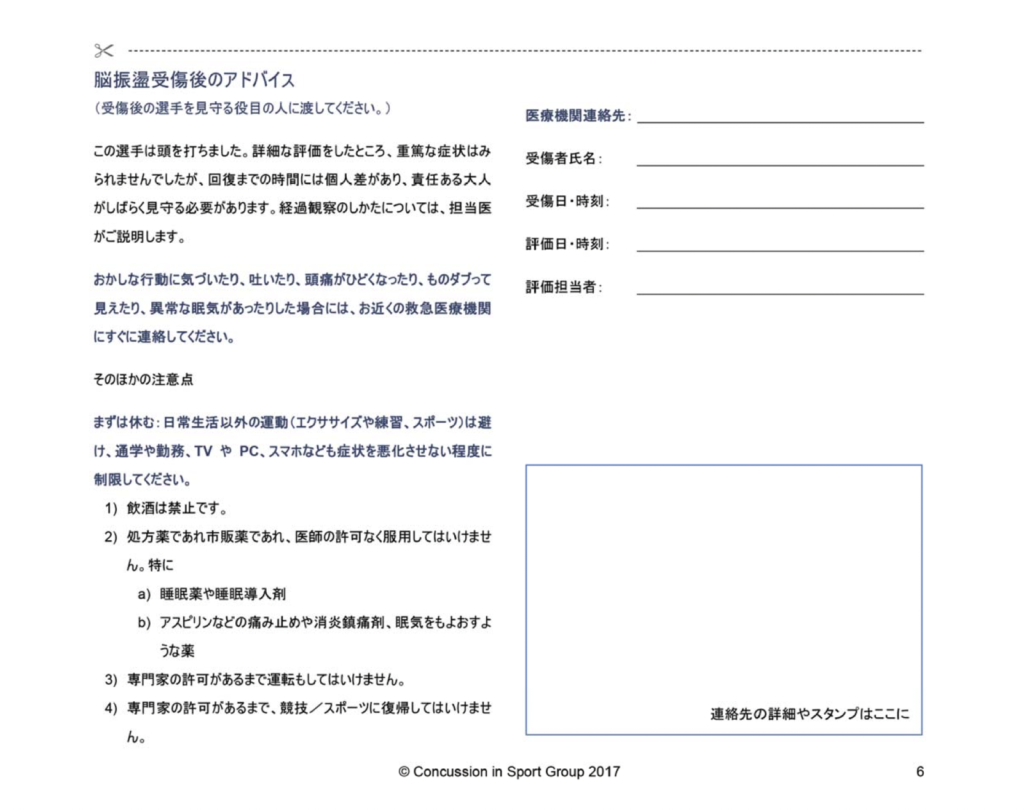
見逃してはいけないサイン
必ず見逃してはいけないサインがあります。
これはATやSCのみならず、監督やコーチも含めて、
スポーツ選手をサポートする方々には必ず知っていて欲しいサインです。
もし、これらのサインを見逃してしまうと、
くも膜下出血などの脳内での血腫を見逃してしまうこととなり、
命の危険も考えられる状態に至ってしまうかもしれません。
ではその危険なサインを見ていきましょう。
- 片方の瞳孔だけ大きい
- 眠気または、起き上がれない
- 悪化する頭痛
- 言語障害
- 力が入りにくい、または麻痺
- コーディネーション不良
- 繰り返す吐き気
- 痙攣
- 異常行動、混乱、落ち着きがない
- 気絶(短時間でも)
これらのサインを見落とさないように受傷が疑われる選手や患者には注意を向ける必要があります。
もし、これらの症状がある場合には、即座に適切な医療機関に搬送することが必要です。
どのスポーツが最もリスクが高いのか?
Prien3)らのresearchでは試合と練習での脳振盪の発生率を調査されました。(アメリカ)
まず、成人のスポーツを分析した結果、
試合中
1. 男子ラグビー
2. 男子アメリカンフットボール
3. 女子アイスホッケー
4. 男子アイスホッケー
5. 女子サッカー
6. 男子サッカー
練習中
1. 男子ラグビー
2. 女子アイスホッケー
3. 男子アメリカンフットボール
4. 女子サッカー
5. 男子アイスホッケー
6. 男子サッカー
次に18歳以下の選手を対象にした分析によると、4)
(試合・練習中の区別はなし)
1. ラグビー
2. アイスホッケー
3. アメリカンフットボール
4. ラクロス
5. サッカー
6. レスリング
7. バスケットボール
8. ソフトボール・陸上ホッケー
9. 野球
10. チアリーディング
11. バレーボール
この調査自体はアメリカのものですが、
もちろん日本で行われているスポーツも多いですよね。
いつどこで起きるかわからないからこそ、万全の準備が必要になってきます。
現場で簡易的な評価をする方法としては、
CRTやSCATなどがありますので、様々な評価を組み合わせて行うと良いでしょう。

競技復帰について
脳振盪後の対応としてのプロトコルは有名だと思いますが、
実際には色々な考え方があります。
NATAのPosition statementに記載されている競技復帰までの流れとしては、以下の通りになります。5)
1. No activity
2. 軽い運動 (<70%最大心拍数)
3. 特異的なスポーツ動作 (コンタクトの可能性なし)
4. ノンコンタクトの運動、レジスタンストレーニング
5. 制限なしの運動
6. 競技復帰
各ステージでは最低24時間空ける必要があります。
脳振盪の関するサイン・主訴が消失していることが前提です。
また、プロトコル中に何らかの症状が出現した場合には、
Activityを中断し、24時間の間隔をあけてから再度行う必要があります。
脳神経について
補足にはなりますが、脳神経について最後書きたいと思います。
脳神経は全部で12対あり、その機能はそれぞれ異なります。
以下の表はそれぞれの脳神経をまとめた表です。

脳の傷害が懸念される場合には、これらの評価をすることも必要です。
それぞれ簡易的な評価をして、最悪の場合どのような問題が起こり得るかを推測することが大切です。
(ちなみに、僕がアメリカにいる時に、実技試験としてこの評価を行いました。)
ただし、これらが問題ないからと言って判断するのではなく、
適切な医療機関(脳神経外科など)に搬送する必要はもちろんあります。
最後に
今回は脳振盪についてVOMSを中心に書きました。
脳振盪について日本ではまだまだ甘い考えがあると個人的には思います。
脳振盪は脳の深刻な外傷です。
適切な対応ができなければ、その選手の人生そのものを壊してしまう可能性もあります。
脳振盪は深刻な外傷という危機感を持つ人がスポーツ現場に増えてくれれば嬉しく思います。
参考文献
1)
Mucha A, Collins MW, Elbin RJ, et al. A Brief Vestibular/Ocular Motor Screening (VOMS) assessment to evaluate concussions: preliminary findings. Am J Sports Med. 2014;42(10):2479-2486. doi:10.1177/0363546514543775
2)
Meaney DF, Smith DH. Biomechanics of concussion. Clin Sports Med. 2011;30(1):19-vii. doi:10.1016/j.csm.2010.08.009
3)
Prien A, Grafe A, Rössler R, Junge A, Verhagen E. Epidemiology of Head Injuries Focusing on Concussions in Team Contact Sports: A Systematic Review. Sports Med. 2018 Apr;48(4):953-969. doi: 10.1007/s40279-017-0854-4. PMID: 29349651.
4)
Pfister T, Pfister K, Hagel B, Ghali WA, Ronksley PE. The incidence of concussion in youth sports: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2016 Mar;50(5):292-7. doi: 10.1136/bjsports-2015-094978. Epub 2015 Nov 30. PMID: 26626271.
5)
Guskiewicz, K. M., Bruce, S. L., Cantu, R. C., Ferrara, M. S., Kelly, J. P., McCrea, M., … & McLeod, T. C. V. (2004). National Athletic Trainers’ Association position statement: management of sport-related concussion. Journal of athletic training, 39(3), 280.
6)
荻野雅宏, 中山晴雄, 重森裕, 溝渕佳史, 荒木尚, & 永廣信治. (2019). スポーツにおける脳振盪に関する共同声明─ 第 5 回国際スポーツ脳振盪会議 (ベルリン, 2016)─ 解説と翻訳. 神経外傷, 42(1), 1-34.



コメント